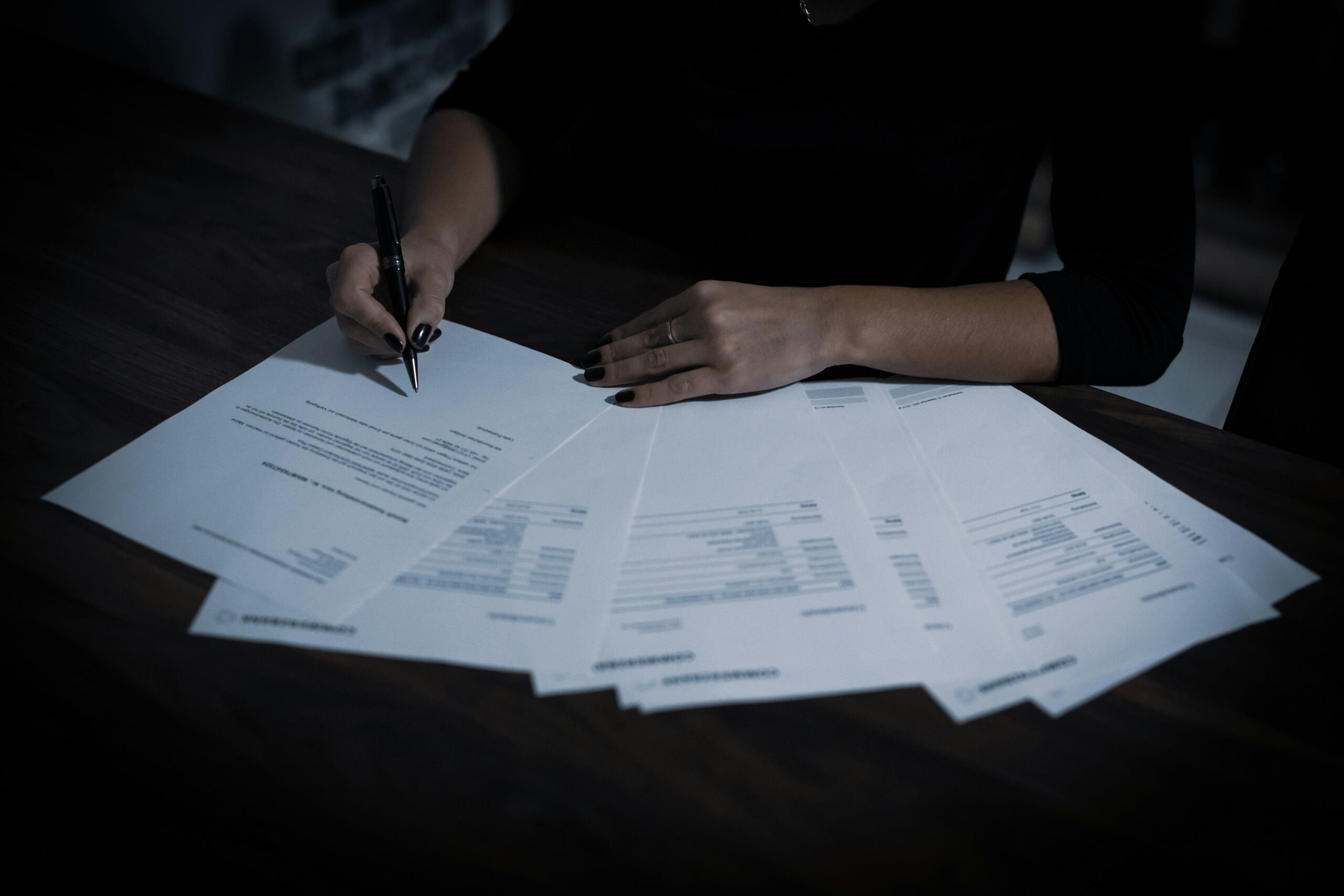2025年(令和7年)の年末調整は、ここ数年で最大級の大改正となります。
基礎控除・給与所得控除・扶養控除・提出書類の方式まで変更されているため、昨年と同じ感覚で書類を提出すると本来受けられる控除を取りこぼし税額が増えるリスクがあります。
特に、今年からは
- 基礎控除の判定所得区分の見直し(基準額58万円)
- 給与所得控除の最低保証額が55万円 → 65万円へ引上げ
- 19~23歳の親族を対象とする新たな控除制度(所得58万超~123万円以下で段階的に控除)
など、これまでにない大規模な再編が行われています。
これらの改正はすべて、国税庁が公開した「令和7年分 年末調整のしかた」「源泉徴収税額表」を根拠とした正式な運用ルールで、2025年の年末調整から完全に適用されます。
とくに影響が大きいのは、
✔ 従来の「103万円・130万円の壁」に該当していた人
✔ パート・アルバイトの扶養判定をしている家庭
✔ 大学生の扶養控除を受けている家庭
✔ 副業をしている給与所得者
です。
もし、企業側が旧来の計算式や誤った所得区分を使ったまま年末調整を行うと、本来受けられるはずの控除額が減少し、結果的に数万円〜数十万円の損失につながりかねません。
この記事では、国税庁資料を元に
・2025年に変わる主要改正点3つ
・損を回避する具体的な対策
を、専門家がわかりやすく解説します。
大改正その1:基礎控除・給与所得控除の引き上げ
令和7年(2025年)税制改正により、所得税の基礎控除額と給与所得控除の最低保障額が大きく引き上げられました。
国税庁の公表資料や税理士法人・FP機関の分析によれば、基礎控除は従来の48万円から58万円にアップ。
さらに所得に応じて段階的な基礎控除の特例が設けられ、合計所得金額132万円以下では95万円まで控除が上乗せされるケースがあります。(ただし、この上乗せは令和7年・8年の時限措置で、令和9年以降は基礎控除の特例が縮小され、58万円が基本額になる見込みです。)
同時に、給与所得控除の最低保障額も55万円 → 65万円へと10万円引き上げとなりました。
この改正により、給与収入が190万円以下の人については新たな控除額65万円が適用されます。
この改正の背景には、物価上昇による実質的な税負担の増大を抑える目的があります。
また、与党税制改正大綱では、年収103万円の壁として長らく議論されてきた所得水準が、控除の改正によって課税最低限が123万円〜160万円あたりに実質引き上げられる可能性が示されており、これまで扶養や就業調整を基準にしていた多くの世帯の収入設計が変わる見込みです。
このような基礎控除・給与所得控除の引き上げは、年末調整および源泉徴収税額の計算に直結する重要な改正です。
従業員、特に低・中所得層にとっては、これまでより控除が手厚くなる一方で、企業側・給与担当者は新しい控除額に対応した税額表・源泉徴収計算への更新が必要です。
年末調整書類の様式の見直しや、従業員への説明・再計算を怠ると、控除を取りこぼすリスクがあるため早めの対応が欠かせません。
大改正その2:扶養控除・配偶者控除・扶養親族等の所得要件の緩和
令和7年税制改正により、扶養控除・配偶者控除などの所得要件が従来より緩和されることが大きなポイントです。
具体的には、これまで合計所得金額48万円以下(=給与収入103万円相当)だった対象者のラインが、58万円以下(=給与収入123万円相当)に引き上げられます。
この改正の結果、たとえばパート・アルバイトで働いていた配偶者や扶養家族が、従来より年間20万円近く収入を増やしても控除対象の範囲に収まるケースが増える見込みです。
また、勤労学生控除においても、勤労学生の合計所得75万円以下(給与収入で130万円前後が目安)だった要件が、85万円以下(給与収入150万円前後)に引き上げられました。
これによって、これまで103万円の壁によって働き方や就労時間を抑えていたパート主婦や学生アルバイト世帯は、収入をある程度増やしながらも扶養控除を維持できる可能性が高くなります。
ただし注意が必要です。
2025年分年末調整では、新しい所得区分を反映した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入が必要になるため、記入漏れや誤認による控除の取りこぼしリスクがあります。
加えて、企業の人事・経理担当者も、従来の103万円の壁前提ではなく、123万円などの新ラインを含めた説明とチェック体制を整備することが重要です。
大改正その3:特定親族特別控除制度の新設
令和7年分から、新たに特定親族特別控除が創設されます。
これは、納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与所得のみの場合は収入123万円~188万円以下)の人がいる場合に、その親族1人あたりの所得に応じて控除を受けられる制度です。
控除額は細かく段階設定されており(国税庁基準):
- 合計所得58万円超~85万円以下 → 63万円
- 85万円超~90万円以下 → 61万円
- 90万円超~95万円以下 → 51万円
- 95万円超~100万円以下 → 41万円
…と続き、最大控除額は63万円、最低でも3万円になるレンジまであります。
この控除を受けるには、従業員側(親)から会社に給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する必要があります。
制度創設の背景には、大学生などのアルバイト世代(19~22歳)が103万円の壁を超えて稼いでも、親側の扶養控除がゼロになるという働き控えの問題を緩和し、若年層の就労と家庭の税負担のバランスをとる狙いがあります。
今回の改正で年収の壁はどう変わる?
令和7年から適用される税制改正によって、これまで議論されてきた103万円の壁が大きく書き換えられ、実質的な年収の非課税ライン(=年収の壁)は160万円あたりまで引き上げられる可能性が出てきました。
年収の壁は税制改正で103 → 160万円に
- 基礎控除の見直しにより、合計所得金額に応じた段階的控除が適用されます。特に低~中所得層(給与収入がある人)は、基礎控除+給与所得控除を合算すると課税最低限が160万円相当になる試算が出ています。
- 給与所得控除の最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げられ、これも年収の壁を押し上げる大きな要因。
- さらに、基礎控除には2年間限定で上乗せ特例があり、低所得(合計所得132万円以下)層には追加控除があるため、一時的にこの160万円ラインが実効的に強く働く可能性があります。
資産形成・就業設計へのインパクト
収入を増やしやすくなる
これまで103万円を超えると税金がかかるから働き控えをしていたパート主婦や学生アルバイトにとって、この壁の引き上げは朗報。
160万円近くまで収入を増やしても所得税の課税ラインを超えず、手取りを確保しながら働く戦略が取りやすくなります。
年収設計の選択肢が広がる
共働き世帯や学生のアルバイト収入を持つ家庭では、多少働いて稼いでも扶養に残せる/控除を維持できるというポイントが資産形成・収入戦略の重要な選択肢になります。
これにより、扶養を前提とした収入設計の柔軟性が増すでしょう。
年末調整・税務リスクの見直しが必要
従業員・アルバイト側だけでなく、企業の経理・給与担当者も新ラインを前提に年末調整や源泉徴収を設計し直す必要があります。
特に低・中所得の社員に対しては、改正内容をきちんと説明し、控除漏れを防がないと、結果的に年末調整時に還付額を取りこぼすリスクがあります。
長期的な資産形成における節税効果
税負担が抑えられることで手元資金が増え、投資・貯蓄・副業への再投資がしやすくなります。
特に若年層やパートタイムワーカーにとっては、増えた手取りを使って資産形成を加速させるチャンスです。
まとめ
いかがでしたか?
会社員にとって、1年に一回の書類提出で良く理解していない人も多いでしょう。
2025年の年末調整は、例年通りの書き方をすると最も損をする特別な年です。
基礎控除と給与所得控除の引き上げ、扶養控除・配偶者控除の所得要件の緩和、そして新設された特定親族特別控除という3つの大改正によって、手取り額が大きく変わる可能性があります。
これらの改正はすべて、正しく申告すれば確実に手元資金が増える内容であり、家計の可処分所得が増えることで、NISA・iDeCoへの積立額アップ、毎月の投資資金の拡大など、資産形成を加速させる大きなチャンスになります。
一方で、前年と同じ感覚で書類を提出すると、控除の取りこぼしによって本来戻ってくるはずの5〜20万円前後を失うリスクもあります。
節税は、最も再現性の高い投資リターンです。
今年は特に、扶養家族の収入ライン、大学生や専門学生が対象になる特定親族特別控除、そして新しい年末調整書類の内容を必ず確認し、控除漏れを防ぐことが重要です。
2025年の年末調整を制することは、1年分の資産形成のスピードを早めることと同義です。
家計の税務リスクを避けるためにも、3つの改正ポイントを正しく理解し、今年だけは絶対にいつも通りで提出しないようにしましょう。
併せて読みたい: